京都府立大学では、ジャスリン・フォード初監督作品「Nowhere to call home(ノーウェア・トゥ・コール・ホーム)」の上映会および監督講演会を下記のとおり開催しますので、ご案内します。
ジャスリン・フォード監督・脚本
「Nowhere to call home(ノーウェア・トゥ・コール・ホーム)」上映会、監督講演会
| 日時 | 2015年10月26日(月)10:30 〜 12:30 (映画上映約60分、監督の講演とQ&A60分)※日本語字幕あり |
|---|---|
| 場所 | 京都府立大学 稲盛記念会館1 F 105 講義室 |
| 対象 | 本学学生、教職員 学外の皆様のご来聴を歓迎いたします。 |
| 言語 | 英語、中国語、チベット語 日本語字幕:山口美知代(本学文学部欧米言語文化学科 准教授) |
 <映画概要>
<映画概要>
それは、遠い国の苦難だろうか?
「チベット人には部屋を貸さないように、警察から言われているんだよ」
28歳で夫と死別し、嫁ぎ先でのひどい仕打ちに耐えかねてチベットの山村から北京の大都会に流れついたザンダは、露天商をしながら息子ヤンチンを学校に通わせようと努力する。しかし住まいを借りるにも、路上に店を広げるにも、警察や人々の冷たい視線に排除され続ける。
ザンダと偶然知り合った米国人記者ジャスリン(=監督)は、自分が一緒にいることで、事態が少しずつ変化を見せるのを感じる。作り手自身が映画に登場する「シネマ・ヴェリテ」の手法で、2人の希有な友情と、北京に暮らすチベット人の苦境、そしてチベットの農村になお残る女性差別を、声高な主張ではなく、豊かな日常の言葉で綴ったこの作品は、中国とチベットの今を等身大に描き出し、日本の中にも同種の問題があることを静かに想起させてくれる。
2014年のニューヨークの近代美術館での先行上映をはじめ、数多くの国際映画祭に出品されたこのドキュメンタリーは、撮影当時はチベット騒乱(2008年)の反動から、中国国内での上映はほぼ不可能と思われた。しかし2015年現在、北京大学はじめ各大学や高校など国内で多数の上映会が開催され、「わたしたちは何も知らなかった」と若い層から声が上がっている。2015年のNHK「日本賞」最終候補作品(選考中)。同年秋、日本語字幕による日本国内での上映会が関東、関西で予定されている。
<あらすじ>
だれもがそこで生き、そこで死ぬ、チベットの高原東部の山村。ザンダは、ただ好きになった別の村の男と結婚するために、習わしに背いて村を出た。しかし夫は若くして病死。義父母との暮らしは過酷で、強盗し刑務所にいる義兄と結婚させられそうになる。息子ヤンチンを学校に行かせることもできず、ザンタは家を飛び出し北京に流れ着いた。
北京でラジオ記者として活躍する米国人女性ジャスリンは、ある日、路上にアクセサリーを並べて売るザンタに声をかけた。腕輪を買ったのは、下心があったからだ。2008年のチベット騒乱以後、中国政府が外国人記者のチベット訪問を禁止しようとする中で、ジャスリンはザンタと電話番号を交換した。
それから2年後。ザンタの方から突然電話があった。「子どもをもらってくれない?」いったい何が母親に、通りすがりの外国人に子どもを渡す決断をさせるのだろう。ジャスリンは、息子ヤンチンの就職援助を通し、住宅や職探しにも差別を受けるチベット人母子の極貧生活に大きく関わっていく。
旧正月を過ごすため、列車に乗ってチベットの義父の家に向かう3人。四川大地震で崩壊した村を抜け、ようやくたどり着いた山村で、義父は孫を奪おうとする。「女には一銭の価値もない」と言われるこの村で、男の孫は義父の家のもの。よい将来のために教育を受けさせたいという、ザンタの切なる望みは叶わないのだろうか―。
<ジャスリン・フォード監督>
1959年、米国生まれ。30年以上にわたり、日本と中国をベースにアジア報道に関わる。日本の共同通信社では、官邸記者クラブに所属する初の外国人記者として、慣行にとらわれない率直な質問を重ね、昭和から平成にかわる日本の動きを世界に伝えるとともに、日本のメディアにダイバーシティの視点を持ち込んだ。その後、アメリカの公共ラジオの番組「マーケットプレイス」の東京・北京支局長を10年以上務め、2001年には中国国際放送曲の生ニュース番組で、外国人初のプロデューサー兼ホストとなった。「ノーウェア・トゥ・コール・ホーム」は初の映画作品。
◆問い合わせ先
文学部文学部欧米言語文化学科 山口 myama@kpu.ac.jp

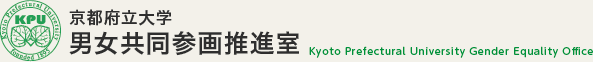
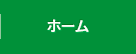

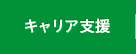
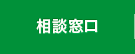
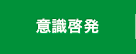
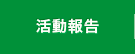
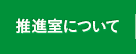
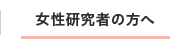

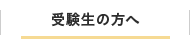
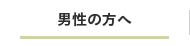
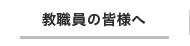
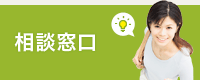

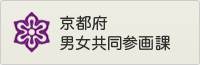
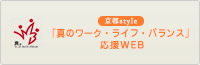


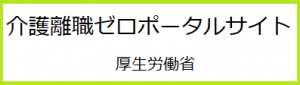
 ページの先頭へ
ページの先頭へ